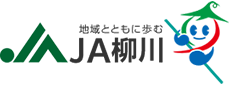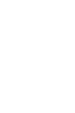オクラ(アオイ科フヨウ属)
土壌医●藤巻久志
オクラの原産地はアフリカ北東部で、語源は現地で呼ばれている「ンクラマ」だとされています。日本では「ん」から始まる名詞はないですが、アフリカには多くあります。キリマンジャロも「キリマ」が山、「ンジャロ」が白を意味しています。キリマン・ジャロではありません。
米国では19世紀初めから広く栽培され、日本には幕末に伝わりました。和名は「アメリカネリ」で、ネリはトロロアオイのことです。オクラもトロロアオイもフヨウ属(ハイビスカス属)で花がよく似ています。
日本で多く栽培されるようになったのは、高度成長期に入り食の洋風化が進んだ頃です。品種はほとんどが固定種の五角オクラでした。ナスやキュウリなどの果菜類は戦後にF1化が大きく進みましたが、オクラはだいぶ遅れて1980年代に初めてF1品種が発表されました。出荷産地では早生で生育旺盛でそろいの良いF1品種が主に使われています。家庭菜園ではさやが丸いものや長いもの、さや色が赤いものや白いものなど、いろいろな品種が栽培されています。オクラの花は野菜の中でもとても美しい花の一つで、レモンイエローの大きな花弁と深紅の花芯を楽しむために栽培している人も多いです。
オクラには滋養強壮効果があり夏バテ予防に有効といわれています。
ところで、オクラという名の歌人がいます。山上憶良(やまのうえのおくら)で、『万葉集』には彼が詠んだ「銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに まされる宝 子にしかめやも」が載っています。子どもはかけがえのない宝物です。日本は少子化で危機的状況になっています。オクラは栄養価の高い野菜なので、どんどん食べて子どもの健康の維持と促進に努めたいですね。